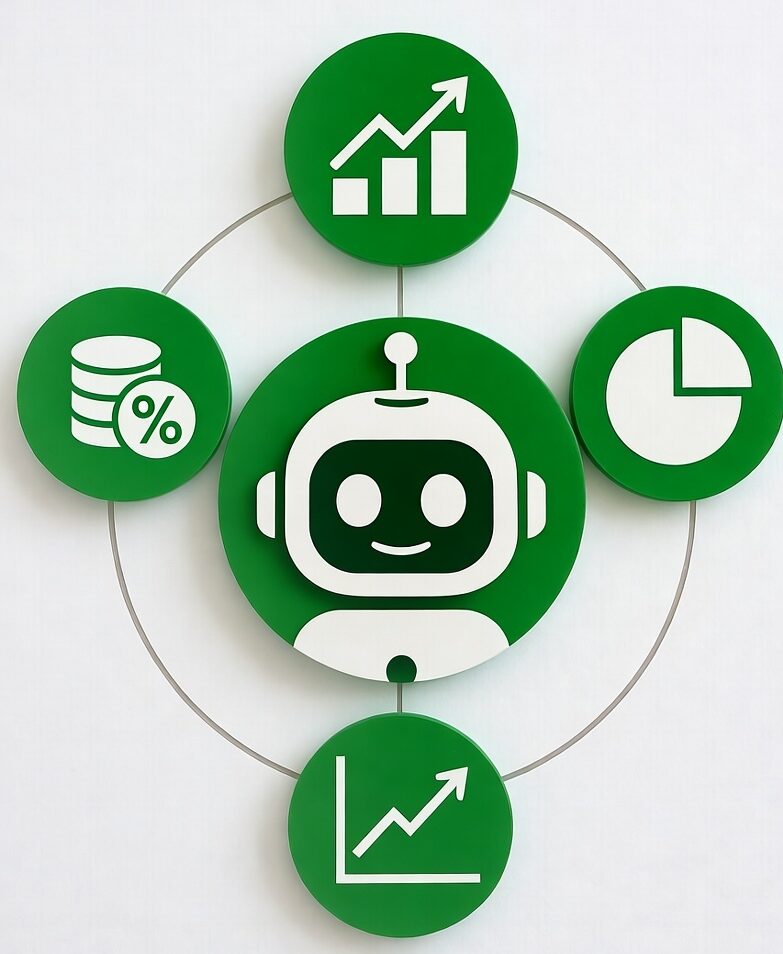簡単に投資するなら「ウェルスナビ」が良いかしら?
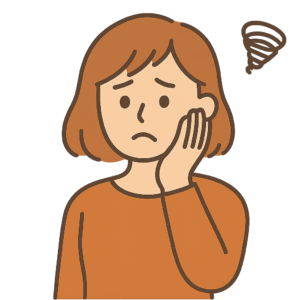

ウェルスナビいいですよね!ただ、長期運用では手数料の高さが気になります
目次
長期・分散・積立の重要性を復習
資産形成を始めるとき、一番シンプルで強い方法は「長期」「分散」「積立」です。
短期での値動きに一喜一憂せず、時間を味方に付けて複利で増やしていく。これだけで失敗しにくくなります。
毎月決まった金額を買い続けるだけで、相場の高低を平均化できる(ドルコスト平均法)ので、心理的にも続けやすいのがメリットです。
複利やドルコスト平均法などについてはこちらの記事👇を参考にしてください。
-

-
参考NISAの2つの枠の違いをやさしく解説
新NISAで買える商品を初心者向けに解説。つみたて投資枠と成長投資枠の違いやメリット・デメリットをまとめました。
続きを見る
手数料は長期運用で大きなダメージに
長期で運用すると、わずかな手数料でも大きな差になります。
ほんのわずかな差でも、数十年後には資産に大きく響くため、運用コストは必ずチェックする必要があります。
信託報酬、口座管理料、売買手数料、ロボアドの利用料など「トータルコスト」で比較するのがポイントです。
シミュレーション
前提条件
- 毎月積立:5万円
- 積立期間:20年(240ヶ月)
- 年率期待リターン(手数料差前):5%
- 手数料差を考慮したネット年率:
- 1.0%手数料 → 実質年率4.0%
- 0.2%手数料 → 実質年率4.8%
結果
| 手数料 | 実質年率 | 20年後の総資産 |
|---|---|---|
| 1.0% | 4.0% | 約1,819万円 |
| 0.2% | 4.8% | 約1,985万 円 |
金融庁「つみたてシミュレーター」で計算
差額はなんと約166万円!
これで「複利の力」と「手数料の怖さ」がよくわかりました!
ロボアドバイザーの魅力は?
「難しそう」と感じる資産配分や買付を自動でやってくれるのがロボアドバイザーの魅力です。
初めての人でも簡単に始められて、継続しやすい設計になっています。質問に答えるだけで最適な配分を提案してくれ、定期積立や自動リバランスまで任せられるので、忙しい人や投資の勉強をゆっくりやりたい人に向いています。
-

-
参考ロボアドバイザーの2タイプ「運用一任型」と「提案型」の違いをわかりやすく解説!
「ロボアドバイザーって何?」という疑問に答えます!提案型と運用一任型の違いを、初心者にもわかりやすく解説。
続きを見る
-

-
参考ロボアドを比較|SBI証券・松井証券・ウェルスナビのリスク&リターンと構成銘柄
SBI証券・松井証券・ウェルスナビのロボアドをリスク許容度や資産配分、コスト面から比較!あなたにぴったりのサービス選びの参考に。
続きを見る
私が使ったことのあるSBI証券、松井証券、ウェルスナビについて以下の記事にそれぞれまとめています。
SBI証券
-

-
SBI証券でリスク許容度を診断|かんたん積立アプリで資産形成をスタート
SBI証券の「かんたん積立アプリ」でリスク許容度を診断!5つの質問に答えるだけで、自分に合った積立スタイルとポートフォリオが見えてきます。初心者でも気軽に試せる内容をやさしく解説
続きを見る
松井証券
-

-
松井証券でリスク許容度を診断|投信工房で資産形成をスタート
松井証券の投信アプリ「投信工房」でリスク許容度を診断!8つの質問に答えるだけで、自分に合った積立スタイルがわかります。SBI証券との違いや、アプリの魅力もあわせてご紹介♪
続きを見る
ウェルスナビ
-

-
ウェルスナビでリスク許容度を診断|全自動運用サービスで資産形成をスタート
ウェルスナビは、投資初心者でも安心して始められる自動運用サービス。公式情報から投資対象とポートフォリオ構成を分析しました。
続きを見る
ウェルスナビの良いところ(ざっくり紹介)
ウェルスナビは「全自動」でNISA枠まで活用して運用してくれるサービスで、手軽さと透明性の高さが人気です。
公式でポートフォリオの構成銘柄や比率を公開しているので、どんな資産に投資しているかが分かりやすいのも安心感につながります。
運用実績も公開されているため、結果を確認しながら使えるのは初心者にとってありがたいポイントです。
ウェルスナビの気になる点
便利さの代償として、手数料が年率約1%とやや高めです。長期で見るとこの1%は積み重なって効いてくるため、コスト意識の高い人は迷うところです。

手数料を払ってでも時間と手間を買う価値があるか、自分の投資額やスタイルで判断しましょう
松井証券「投信工房」の良さ
松井証券の「投信工房」は、無料で自動リバランスができたり、好きなときに自分で銘柄を入れ替えられたりと自由度が高いサービスです。
投資信託を小額から買える点も魅力で、100円から1円単位で購入できる商品があるため、少額投資家でも細かい比率を作りやすい設計です。手数料面でも使いやすく、コストを抑えつつ自分で調整したい人に向いていると思います!
投信工房の注意点
扱っている投資信託の本数は大手と比べてやや少なめです。さらに、リバランス時の税金を自動で最適化する機能はないため、売買による税負担を自分で管理する必要があります。税金面まで自動化を求めるなら、そこはデメリットになります。
ETFを丸ごと真似するのは少額だと難しい
ETFは分かりやすく低コストなものが多いですが、1口あたりの価格が高い銘柄もあり、少額投資家が理想の配分を保つのは大変です。
だからこそ、100円から買える投資信託は少額投資家にとって非常に有利です。細かく買い分けてポートフォリオを整えやすい点は見逃せません。
ウェルスナビを「再現」する選択肢
ウェルスナビは構成銘柄や比率を公開しているため、それを参考に自分で同じ配分を投資信託で組むことは可能です。
ポイントは低コストのインデックス投信を使うこと。これなら手数料を下げつつ、同等の分散効果を得られることが多いです。
実践
- 手数料が低く、純資産が十分な投信を候補にする(信託報酬、運用規模、流動性をチェック)
- 少額で買えるか、NISA対応かを確認する
- リスク許容度を決める
- 候補をシミュレーションする
最後に
投資は完璧を目指す必要はありません。まずは始めること、続けることが一番大切です。
ウェルスナビで「ほったらかし」を選ぶのも、自分で安い投信を集めてコストを抑えるのも正解です。大事なのは自分の性格と目的に合った方法を選び、投資の基本である「長期」「分散」「積立」を守ることです。
次回からはウェルスナビの構成銘柄に該当する投資信託を絞っていきます!💪